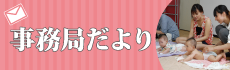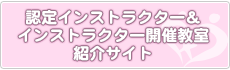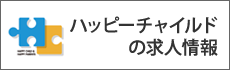- ホーム
- 受講生の声
受講生の声
実際に受講された方々の感想をご紹介させていただきます
- アタッチメント・ベビーマッサージ
- アタッチメント・食育
- アタッチメント・ヨガ
- ベビーキッズ・あそび発達
- プレスクール・あそび発達
- 子育てマインドフルネス
- Newアタッチメント・キッズマッサージ
- Newアタッチメント・ジム
- アタッチメント・キッズマッサージ
- アタッチメント・ジム
- アタッチメント心理カウンセラー
- 教室運営力アップセミナー
- コミュニケーション術
- アタッチメント・発達支援療育入門
- 発達支援療育アドバイザー
- 育児セラピスト 前期課程(2級)
- 育児セラピスト 後期課程(1級)
- シニアマスター
- 育児セラピスト・ライフサポーター
- トレーナー
- アタッチメント・ペアレンティング
- 次世代こども教育コンサルタント
- シンポジウム
- 認定講師
- 全国大会・スキルアップ講座再受講
- 保育園経営を考える会
- アタッチメント教育研究会
- 子育てを真剣に考えて実践する会

参加者の皆さんと少し話もできてよかったです
その他 (ピアノ・リトミック講師) 東京都 [シンポジウム 8期]

今回の発達支援は本当に今一番必要な学びでした
その他 (ベビマインストラクター) 秋田県 [シンポジウム 8期]

ワークでもこれをやってみよう!というヒントがたくさんありました
その他 (公文式指導者) 埼玉県 [シンポジウム 8期]

様々な場所で、様々な活動をしている方々とお話ができ実のある時間となりました
その他 (親子教室主謀) 東京都 [シンポジウム 8期]

我が子を育てた自信をもってこれから様々な活動をしていきたいです
その他 (自営業) 愛知県 [シンポジウム 8期]

資格を生かしきれない中、全国大会のことを知りました。来年の全国大会ではムネをはれるようがんばっていこうと思います。
その他 (認定こども園保育補助) 埼玉県 [シンポジウム 8期]

子育て全般の中で、その年々の旬の話もシンポジウムの中で得られてうれしいです
その他 (家庭的保育者) 東京都 [シンポジウム 8期]

企画のつくり方も勉強になりました
その他 (児童館) 埼玉県 [シンポジウム 8期]

机上で学ぶことでは得られないすばらしい学びをすることができました
その他 (幼児音楽講師(自宅サロン経営)) 千葉県 [シンポジウム 8期]

早く気付き、目をかけ、声をかけ、心をかける保育を行なうことで、障害のある無しに関係なく、良い保育、教育が行えるからです
その他 (幼保連携型認定こども園 園長) 宮崎県 [発達支援療育アドバイザー 0期]
-

発達心理学に基づく育児の専門家になる資格です
-

なぜ、子育てにアタッチメントが必要なのでしょうか?
-

大学カリキュラムに導入されています
-

理事長メッセージ
わたしたちが描く世界観 -

わたしのスキルアップ物語
仕事が、人生が、変わった... -

全国のインストラクターの活動を取材しました
Basic course
基礎講座
Skill up course